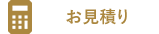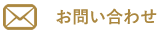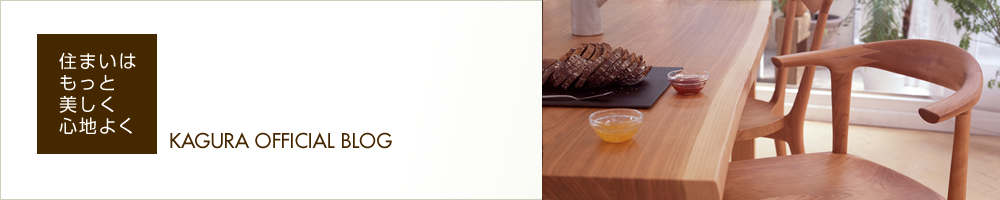
「タタミベッド」の選び方
2020.4.9

「マットレスではなくて布団で寝たい」
または
「金属のスプリングの入っていないマットレスを使用したい」
という方が選択されることの多い「タタミベッド」。
昨今の寝具の多様化からも検討の方が増えてきたように思います。
また、フローリング中心の間取りが増えてきたことにより、そういった場所に置いて、ちょっとした小上がりの空間を作る目的でタタミベッドを検討する方も。
布団を敷いて寝るだけではなく、ちょっと横になってくつろいだり、そこでお茶を飲んだり、様々な用途があるのが「タタミベッド」です。
ベッドフレーム自体の高さがあると、布団の上げ下げも立ち上がるのも負担が少なく済みます。
布団を愛用している人にも日常生活における足腰の負担も軽減できるのでおすすめです。
主に足元に多く舞うとされている室内の埃を避ける意味でも高さがあることは有用なのです。
和モダンなおしゃれな空間を演出するベッドとしても利用できます。
洋室の雰囲気を壊さない控えめな美しさがあり、インテリアにこだわりがある方にもおすすめです。
今回はそんな「タタミベッド」の選び方についてお話しさせて頂こうと思います。
まずは「畳」を選ぶ
畳は主に畳表と畳床(心材)で構成されており、昔ながらの製法により天然素材を使用したものと人工的に作られた和紙や合成繊維を使用したものがあります。
「人工的に作られた素材」の畳とは?
「和紙表」「建材表」とよばれ和紙やポリプロピレンを原料として、イグサ風に仕上げた畳表です。
様々なカラーバリエーションや手入れの簡単さが魅力といわれています。
イグサの畳表にくらべ耐久性が有り、変色もほとんどなく、ダニやカビの発生も抑えることができるといわれています。
畳床では「建材床」などがあります。
細かな木材を圧縮したインシュレンボードと、ポリスチレンフォームを使った畳床になります。
化学物質で作られているのでダニなどの害虫が寄生しにくく、スチレンフォームに断熱効果があるといわれています。
しかし、フォームは固い材質で作られているため、踏み心地が硬くなり、調湿効果が低いためお手入れを怠ると、カビが生えやすくなるといわれています。
その対策として藁と藁の間に、ポリスチレンフォームを挟み、藁の感触を残しつつ、軽量で湿気にも強いという「藁サンド」という畳床もあります。
天然素材の畳とは?
天然素材の畳とは、イグサの畳表「国産イグサ」や「中国産イグサ」を使用したものをさします。
特に国産のイグサは本来の弾力性、耐久性を保持し、見た目も美しく変色やムラもなく、手触り、香りが高いものになります。
畳床においては天然素材100%、快適さと、耐久性に優れた「藁床(ワラドコ)」があります。
藁床は呼吸をしながら、吸湿・放湿を行うため、空間の調湿効果をもたらします。
藁同士に空気の層があるため、天然の高い保温効果が、自然素材ならではの快適さをもたらしてくれるのです。
上質な藁床は、耐湿耐久性が優れているため、手入れを怠らなければ、非常に長持ちします。
また、藁床は縦横にわらを敷いてあるので、表替えなどで何回縫ってもボロボロになるようなことがありません。
稲わらの層には適度な空気があるので、建材床では感じられない、独特の踏み心地が特徴的な畳をつくることが可能です。

イグサが畳に使われてきた理由
イグサはサルモネラ菌、食中毒菌など、数多くの菌に対して抗菌作用を持っています。
大生産地である熊本県八代地区ではこのイグサを細かく切って浴槽に浮かべ、「イグサ風呂」を楽しむほど。
微生物の繁殖も抑えるので脱臭効果もあります。
また、茎の構造により湿度を一定に保つ働きがあり、湿度が高い時は湿気を吸い取り、低い時は放出して、快適な湿度を保ち、有害物質も吸い取ってくれることが確認されています。
ホルムアルデヒド、二酸化炭素、たばこのにおいなども吸着してくれるのです。
そしてイグサに含まれるバニリン、フィトンチッド、α-シベロンという物質は、鎮静効果、ストレス軽減に効果があるのです。
昔からの畳文化はかつての日本人が知ってか知らずか培ってきた「健康の文化」ともいえるかもしれません。
通気性で選ぶ
高温多湿の日本において、ベッドの通気性は重要です。
特に近代のマンションなどの建物は機密性が高い反面、湿気が篭もりやすくなります。
また、人間は睡眠中にコップ1杯分の汗をかくといわれています。
その汗の水分は、布団、畳へと移動していきます。
そこでは湿気が下へ抜けることが重要になります。
家具蔵ではすべてのベッドフレームの床板にはフレームと同じ約40mm の分厚い無垢材を使用。
無垢材の調湿効果が快適な睡眠環境を整えます。
また、床からフレームを浮かせたデザインは通気性に配慮しているので衛生的にも安心です。
そのうえで家具蔵の畳は畳床に檜のチップを使用しています。
家具蔵で檜チップを畳床に使用しているのは、檜は非常に調湿機能が高く、ダニを抑制する成分が含まれていることからです。
自然の力でダニを抑制する檜畳は、寝室に適した素材ともいえるのではないでしょうか。
檜から放たれる木の成分が、イライラを抑え、心の鎮静剤として作用し、脈拍の乱れの減少や、ストレスホルモンを減少させるなど、森林浴効果と同様の効果を発揮するのです。
また、ベッドの下に収納がついているものについては通気性という点で、一度見直してみることをおすすめします。
寝室は人生の中で多くの時間を過ごし、日々の疲れを癒す場所です。
そんな大切な空間だからこそ、本物の素材と、木を使った無垢材・無着色のベッドで快適な睡眠環境を整えてみてはいかがでしょうか。
関連する記事
最近の投稿
- 無垢材家具とSDGsの「良い関係」とは? 2024年7月26日
- 高齢の方のキッチン選びのポイントは 2024年7月24日
- 「マンションのオプション家具」を決める前に見ておくものとは? 2024年7月22日
- ベッドルームに置いておきたい家具とは? 2024年7月20日
- なぜ収納家具の奥行は45cm前後が多いのか 2024年7月18日
- 6人掛けの一枚板テーブルのサイズ選びの正解は 2024年7月16日
- ローテ―ブルを一枚板天板から選ぶ 2024年7月14日
- ソファを美しく見せ、使いやすくする「レイアウト」のコツとは? 2024年7月12日
- 家具選びは「椅子から始める!」そのワケとは? 2024年7月10日
- 子供とキッチンワークを楽しみたい!を叶えるコツとは? 2024年7月8日
カテゴリー
- 家具の選び方・置き方 (1,523)
- インテリア&住宅情報 (617)
- 人と木と文化 (388)
- ニュース&インフォメーション (435)
- オーダーキッチン関連 (401)
- 一枚板関連 (609)
- オーダー収納関連 (596)