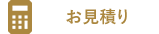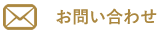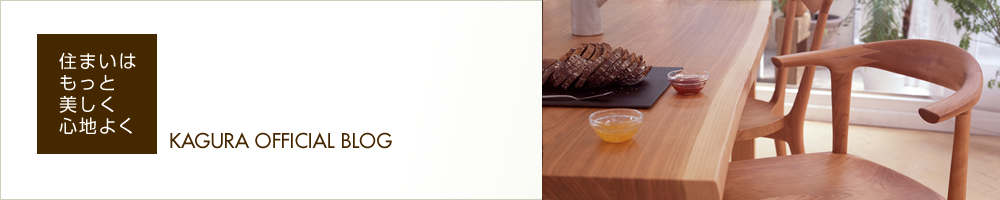
樹木から学ぶもの
2018.1.14
木にはいわゆる「意思」がなく、ある意味で本能のまま育っていきます。
その生育の様子を見ていると、生物社会のある側面をそのまま正直にあらわしていることが多いと言われています。
今回はそんな木の生育の様子から教えてもらえることをお話しします。
「木の生え方」が教えてくれること
例えば、スギを密植して育てる際、その中に少しでも伸びのよいものが出ると、樹冠がひろがって隣の木の陽当たりは悪くなります。
太陽の光が減ると木の生長は鈍くなるので、競争に負けた小さな木は大きく育つことができなくなります。
競争に勝った木はどんどん大きくなりますが、その一方で、根元のほうは小さな木が密集しているので陽が当たりません。
そのため、下枝は枯れ落ちて、幹は無節で「元(もと)」も「末(すえ)」も同じ太さの材になります。
つまり同じような木ばかり育つので、電柱の用材などにするにはこのやり方は都合がよいですが、変化に富む個性のあるものは得られなくなります。
一方、庭の真ん中に一本だけ生えた木は、陽光が全体に当たるので、幹は根元が太く先細りの円錐形に育ちます。
下枝がいつまでも落ちないので節も多くなります。
一本一本の木は形も材質もバラバラのため、ふつうには用材としては使いにくいのですが、個性のある板がとれるので、用途によっては面白い使い道があります。
考えてみるとこれは教育に似ています。
一カ所に沢山木が生えている状態は学校教育にあたり、孤立している木は個人教育にあたるわけです。
樹木を育てるにはある程度の保護は必要ですが、それも度を超えると弊害を伴います。
自然に生えた森林をみると、ある一種類の木だけで空間を独占してしまっているというようなことはまずありません。
いろいろな木が混じり合って一つの林をつくっていますね。
たとえばヒノキ。
落葉すると葉はウロコのようにこまかく分かれるので、雨が降ると流れてしまいます。
自然林なら下に生えている雑木の落葉におおわれて、そのまま腐朽し、やがてふたたび木の栄養分として吸収されるはずですが、人工林では下草がないために雨のたびに洗い流されて、地表は常に裸地になっています。
つまり目先のものに追われて雑木や下草を取り除いた過保護は、結局は木のためにならず、山の破壊にまでつながるということが、ここしばらく憂慮されているのです。
「緑の砂漠」
「緑の砂漠」という言葉をご存知でしょうか。
緑の砂漠とは、樹木はあるものの、土壌が悪かったり、背の低い植物が生えていない状態をいいます。
人工林は過密に植えたものを適宜間引いていくことで良質の木材を得るという手順をたどります。
まず、樹木が幼いうちは下草を刈るなどして、太陽光や養分をめぐる競争を人為的に避ける方針がとられ、結果的に樹木は過密な状態のまま成長します。
やがて、樹木が大きくなり、間引きを行わなければならないのですが、これを怠ったまま放置しておくと密に広がった樹冠によって太陽光は遮られ、地面に近い部分は枯れ果てて土がむき出しになった状態になってしまいます(一応時間が立てば再生はします)。
因みに木材として育てる為には枝打ちをして余分な枝は切り落とさねばならず、それを行う為にも地面が露出していないと不便であるといった理由でも下草刈りが行われる為に、土がむき出しの状態になる期間が人為的に増えてしまっています。
これが「緑の砂漠」と呼ばれる状態で、遠目には緑に覆われているものの、実態は生物多様性という面で非常に乏しい森林となってしまっています。
また、地面に近い場所に植物がいないことで雨滴による土壌侵食を受けやすく、土砂災害の原因となってしまうことがあります。
自然が教えてくれること
「保護をすれば弱くなる」というのは生物学の原則です。
大事にするだけが真の幸せにつながるものではない、というのは人間の世界でも共通した部分があるお話です。
これと似たような話が環境工学の中にもあります。
現代は住宅設備機器の発達によって、室内気候はどんな状態にでも望みのままにコントロールできるようになりました。ですが果たしてそれがよいことなのか。
医療機器の進歩による検査漬け、薬漬けが疑問視されてきたように、住宅もまた設備漬け、電化漬けへの傾向をチェックしなくてもよいのか、という反省があります。
老人ホームなども、あまり親切につくりすぎるのは駄目で、ほどほどの不便さを残しておかないといけないといわれています。
短い時間の中で測った快適さに合わせるだけでよいと思うのは早計です。
そういう反省を樹木は私たちに無言のうちに教えてくれるのです。
その他、「無垢材が私たちにもたらしてくれるもの」はこちらから
参考文献
鹿島出版会 小原二郎著書「木の文化」
関連する記事
最近の投稿
- メープル材とナラ材、白木材はどちらを選ぶ? 2025年7月2日
- テレビボードのサイズの基準は何か 2025年6月30日
- ラウンドテーブルは使いにくい?そのメリットと検討の際のポイントとは 2025年6月28日
- ダイニングテーブルとソファ、配置のポイントは? 2025年6月26日
- 「足が床に届かない」椅子を使い続けるとどうなるか? 2025年6月24日
- 「失敗しない家具選び」は3Dプランニングで! 2025年6月22日
- 大きなテーブルと小さなテーブルはどちらを選ぶべきなのか 2025年6月20日
- マンションで壁面収納を導入する際のポイントは 2025年6月18日
- 一枚板テーブルは工場直営の家具販売店で選ぶ理由とは 2025年6月16日
- 無垢材オーダー家具は何を暮らしにもたらすか? 2025年6月14日
カテゴリー
- 家具の選び方・置き方 (1,573)
- インテリア&住宅情報 (639)
- 人と木と文化 (397)
- ニュース&インフォメーション (448)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (617)