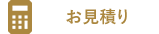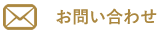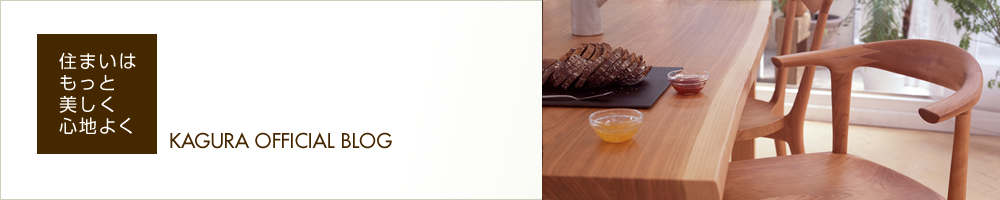
年輪の不思議
2018.2.13
木の成長には、上方向に伸びる「上長成長」と幹や枝が肥える「肥大成長」があります。
肥大成長を行うのは、「形成層」という組織です。
形成層は、幹や枝の外側近くにあって、内側と外側の両方向に細胞分裂を行います。
内側へ分裂した細胞は木の組織となります。
また、外側へ分裂した細胞は師部(師管)となります。
このように、木は外側へ外側へと組織を積み上げるように増やしていきながら大きくなっていきますが、でき上がる細胞のつくりは季節によって違います。
春には直径が大きくて壁の薄い細胞(早材)が作り出されます。
夏以降は成長が鈍り、直径が小さくて壁の厚い細胞(晩材)が作られます。
そして秋から冬には細胞分裂を止めます。
早材から晩材への移行はゆっくりですが、晩材から早材への移行のスピードは早く、年ごとにその境目がはっきりしてきます。
直径が大きくて壁の薄い細胞は白っぽく見え、直径が小さく壁の厚い細胞は黒っぽく見えることで白黒交互の同心円、つまり年輪ができるわけです。
ちなみに、同じ木の中でも根っこに近い部分と梢の年輪では全く数は異なります。
先程お話したように樹木は上長成長と肥大成長を同時に行っていますので、上に行けば上に行くほど細く、年輪の数は少なくなります。
その為、樹木の正確な年齢を知りたい場合は、出来る限り根に近い部分の年輪を測定しなければなりません。
年輪年代学
これを応用し、樹木の年輪パターンを分析することによって年代を科学的に決定する「年輪年代学」というものがあります。
樹種や樹齢による影響を補正しながら、地域の環境変動などの諸条件を反映させ、若い樹木から老齢の樹木へと遡ることによって、年代と年輪パターンの相関をグラフ化したもの、これを「標準年輪曲線」といいます。
年輪は、切り出され、木材として使用された樹木からも測定できるため、標準年輪曲線は、さらに過去へと遡ることができます。
実際、例えばドイツ南部地方ではオークの木で約1万年前までの完全な標準年輪曲線が得られたといいます。
この標準年輪曲線を使えば、新しく遺跡などから発掘された木材の年輪パターンから、その木材が切り出された年代を年単位で正確に決定できるのです。
2011年には、この標準年輪曲線と気温、降雨量など実際の環境変動を対応させることによって、ドイツ、フランス周辺の過去2500年前まで遡った気候を再現することに成功しました。
そして、歴史学者や考古学者をも含む共同研究チームは、この過去の気候の記録によって、実際に起こった歴史上の出来事が見事に説明できることを発見したのです。
木の「生え方」と「アテ」
「山で迷った時は切り株の年輪を見れば方角がわかる」という言葉があります。
じつはこれは全くの間違いです。
そもそも、なぜこのような間違いが伝わったかと言うと、南側は日当たりがよく樹木の成長が活発になるため、年輪幅が広くなるという理由でした。
しかしながら実際に年輪の形成において日当たりはあまり関係ありません。
樹木がきれいな円筒型ではなく歪な形に成長するのは、生えている地面の傾斜やその他の環境による影響が強いのです。
傾斜地に生えた樹木は、そのまま斜めに育つと倒れてしまう為に、真直ぐ育とうとします。
しかし地面が傾いているために、倒れないよう自らの体を補強しなければなりません。
その際に出来るのが「アテ」という部分で、つまり幅の違う年輪は方角を示すのではなくて、力がかかっている部分を示すのです。
急な斜面に育った木では、広葉樹では山側に、針葉樹では谷側にアテが出来ます。
不思議なことに広葉樹と針葉樹とではアテのできる位置が逆です。
どうして、この違いが生まれたのでしょうか。
植物の構造はよく鉄筋コンクリートに言い換えられます。
鉄筋にあたるのが「セルロース」、コンクリートにあたるのが「リグニン」です。
通常の木部では針葉樹と広葉樹のリグニンとセルロースの含まれる量はほぼ同じです。
しかしアテについて言うと、針葉樹では例外なくリグニンの多い圧縮アテを曲がる外側に形成し、広葉樹ではリグニンを全く含まない引張アテを曲がる内側に形成します。
広葉樹は針葉樹と比べ構造が複雑で進化した樹木です。
リグニンは生み出すのに大変な労力が必要ですが、セルロースは光合成で大量に生成されるグルコースをそのまま繋げれば作れるので、はるかに少ない労力で作れるため、そのような違いが生まれたのでしょう。
針葉樹が倒れないように根元にコンクリートを重ねて補強するのに対し、広葉樹は鉄筋で上から引っ張って支えているわけです。
私たち家具蔵の家具は木目もデザインとして製作しています。
テーブルの木口を見て頂くと、年輪がはっきりと分かります。
板目、柾目といった木目もまた、年輪を縦にスライスした際に出来た模様です。
長い樹木の歴史が感じられる木目を生かした家具。
ぜひ家具蔵各店舗でご覧になって下さい。
関連リンク
https://www.kagura.co.jp/kagu/concept-1/
https://www.kagura.co.jp/products-tag/
参考文献
鹿島出版会 小原二郎著書「木の文化」
関連する記事
最近の投稿
- 無垢材家具とSDGsの「良い関係」とは? 2024年7月26日
- 高齢の方のキッチン選びのポイントは 2024年7月24日
- 「マンションのオプション家具」を決める前に見ておくものとは? 2024年7月22日
- ベッドルームに置いておきたい家具とは? 2024年7月20日
- なぜ収納家具の奥行は45cm前後が多いのか 2024年7月18日
- 6人掛けの一枚板テーブルのサイズ選びの正解は 2024年7月16日
- ローテ―ブルを一枚板天板から選ぶ 2024年7月14日
- ソファを美しく見せ、使いやすくする「レイアウト」のコツとは? 2024年7月12日
- 家具選びは「椅子から始める!」そのワケとは? 2024年7月10日
- 子供とキッチンワークを楽しみたい!を叶えるコツとは? 2024年7月8日
カテゴリー
- 家具の選び方・置き方 (1,523)
- インテリア&住宅情報 (617)
- 人と木と文化 (388)
- ニュース&インフォメーション (435)
- オーダーキッチン関連 (401)
- 一枚板関連 (609)
- オーダー収納関連 (596)